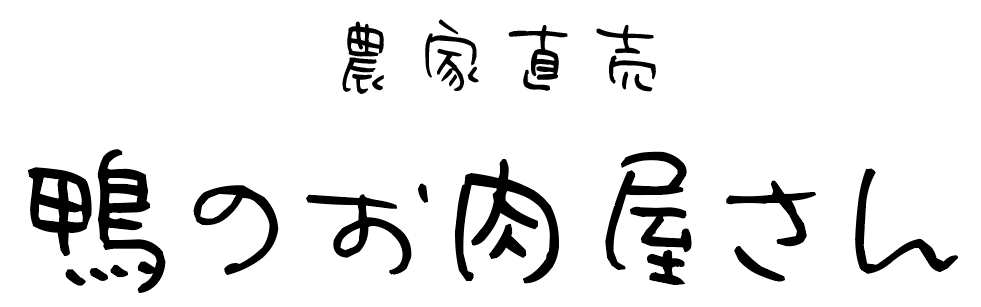BLOG
2025/03/31 12:57
「自然と共に生きてきた村——大蔵村の農業と暮らしの歴史」
はじめに
最上鴨の飼育をしている加藤貴也です。私自身、大蔵村の出身で幼いころは控えめで、よく女の子に間違われたもんです。今ではヒゲもじゃになりましたが(笑)、そんな自分がこの地で鴨を育て農や暮らしと向き合うようになりました。1981年生まれ、今年で44歳になります。そんな僕がいま、改めてこの村の農業や暮らしの歴史に向き合っている理由を少しだけお話しします。
山形県の北東部にある大蔵村。山に囲まれた静かな場所で、冬になると一面の雪景色に包まれます。そんな土地で昔から人々は自然と共に暮らし農を営んできました。
大蔵村の農業っていわゆる“効率重視の大量生産型”とはちょっと違う。山間部という立地もあって、畑を維持するにも労力と工夫が必要です。自然の流れや季節のリズムに寄り添いながら、少しずつ積み重ねてきた知恵の上に今の営みがあります。最近ではこの農のかたをどう維持していくかという課題にも直面しています。

修験道と山の恵み
大蔵村が歴史の舞台に登場するのは、奈良時代から平安時代にかけて。出羽三山信仰が広まるなかで、月山・湯殿山・羽黒山を巡る修験者たちが通る重要なルートのひとつになりました。この村の歴史を語るうえで欠かせないのが「出羽三山信仰」。月山や湯殿山へ向かう修験者たちがこの村の山道や谷筋を静かに抜けていったのです(8世紀末〜12世紀)。
行者たちを迎える村人たちは、食べ物を用意し、道を案内し、ときに宿を提供しながら暮らしていました。自然に寄り添いながら、山の恵みをうまく活用する生活がそこにはありました。
山菜、キノコ、炭、川魚。農業といっても、畑だけじゃない。山そのものが、食べ物や資源をもたらす“もうひとつの農地”だったとも言えるかもしれません。こうした山の恩恵が、昔からの暮らしを支えてきました。

湯治と暮らしの知恵
12世紀ごろに見つかったといわれる肘折温泉。その発見は、地元の猟師が怪我をした際に温泉で傷を癒やしたことに由来するという伝説が残っています。ここもまた、大蔵村の暮らしに大きな影響を与えてきました。
湯治客が長く滞在し、自炊をする文化が根づいたことで、地元の食材や保存食が欠かせないものになりました。干し野菜、漬物、雑穀。冬に備えて準備する知恵が、しっかり暮らしの中にあったんです。
温泉街では、今も「朝市」が開かれていて、地元のお母さんたちが採れたての山菜や漬物を並べています。早朝、湯上がりの湯治客と地元の人が笑顔でやり取りする姿は、この土地らしいあたたかさにあふれています。
また、2月の「肘折幻想雪回廊」では、雪で作られたロウソク灯籠が温泉街を照らし、幻想的な風景が広がります。春の「肘折雪まつり」や、秋の「収穫感謝祭」など、四季折々のイベントも行われ、温泉と農業、観光がゆるやかにつながっているのも魅力のひとつです。
豪雪の冬は畑仕事ができない。でも、だからこそ家の中では手が動いている。漬け物を仕込んだり、道具を直したり。静かだけど、生きている感じがするんです。

近代の変化とこの村らしさ
明治(1868〜1912年)以降、日本の農業は大きく変わっていきました。道路ができたり、水路が整備されたり。でも大蔵村は、地形の厳しさや雪の多さもあって、一気に変われる場所じゃなかった。
むしろ、昔からのやり方に自分たちなりの工夫を重ねて、少しずつ今のかたちになってきたんだと思います。
戦後(1945年〜)は林業や山菜採り、保存食づくり、加工品づくりなど、いろんなことを組み合わせた“暮らしの仕事”が主流に。自分たちで食べて、余った分は売る。そんな生活のスタイルが、今の時代になって改めて価値あるものとして見直されてきています。
ちなみに、大蔵村の人口は昭和30年頃には約6,000人を超えていましたが、現在では約3,000人(2024年時点)を下回っています。こうした背景のなかで、昔ながらの暮らしを守りながら農業を続けていくことの大変さと尊さが、よりいっそう実感できます。

大蔵村の農産物
大蔵村では、豊かな自然と寒暖差のある気候を活かして、さまざまな農産物が育てられています。特に人気があるのは、清流の恵みを受けたお米「つや姫」や「はえぬき」。甘みがあり、冷めても美味しいと評判です。
また、山間地ならではの特産として、山菜やきのこ類も豊富。春にはわらびやこごみ、秋には舞茸やなめこなどが採れ、地元の朝市でもよく見かけます。なかには、これらを使った加工品や干し野菜もあり、冬場の保存食として昔から重宝されてきました。
蕎麦や野菜類、えごまなども栽培されており、近年では有機や自然栽培に取り組む農家も出てきています。地味かもしませんが、ひとつひとつ手間をかけて育てられたものばかり。そういう作物が、暮らしの中にしっかりと根づいているのが、大蔵村の農業の魅力だと思います。

おわりに
最近では村に戻ってきて農業を始めたり、新しい技術を取り入れながら地元の農を続けていたり、少しずつ新しい風も吹いてきているように感じます。
いわゆる“規模の大きな農業”ではないけれど、季節を感じて自然と話すように作物を育てる。そんな農のあり方が、これからの時代にもきっと必要とされていくはずです。
僕たちが取り組んでいる「最上鴨」も、そんなこの土地の流れの中にあるものです。ちなみに農場は大蔵村だけでなく、新庄市にもあります。地元の環境と地元の人々と共に歩幅を合わせながら、一歩ずつ進んでいくつもりです。
【大蔵村の沿革まとめ】
奈良〜平安時代(8〜12世紀)
1:出羽三山信仰の広がりにより、修験道の通過点として地域が栄える。
2:月山・湯殿山へ向かう行者たちが村を通過し、村人がその接待や支援を担う。
3:山の資源(山菜・炭・渓流魚)を活かした半農半山の暮らしが根づく。
鎌倉〜江戸時代(12〜19世紀)
1:村落が定住化し、農業と山の採取を組み合わせた生業が確立。
2:肘折温泉が湯治場として発展し、参拝者・湯治客の宿場機能を担う。
3:地域の祭礼や共同作業(講・結い)を通じた村の自治と連帯感が強まる。
明治〜大正(1868〜1926)
1:近代化とともに村の行政区分が再編成。
2:山形県最上郡に属する村として現在の大蔵村が形成。
3:農業は稲作やそば作りが中心。山林資源の活用も盛んに。
昭和(1926〜1989)
1:1950年代、人口は約6,000人を超え、村としては最大規模に。
2:戦後復興期に林業・農業・観光業(温泉)などが活性化。
3:高度経済成長期以降、都市への人口流出が進み、徐々に人口減少。
平成〜令和(1989〜現在)
1:高齢化と人口減少が進み、現在の人口は約3,000人以下(2024年)。
2:一方で、伝統文化・自然・食を活かした地域資源の見直しが始まる。
3:最上鴨をはじめ、農産物ブランド化や六次産業化の取り組みも見られる。
4:肘折温泉では雪まつりや朝市など、観光と地域文化をつなぐ活動も展開中。